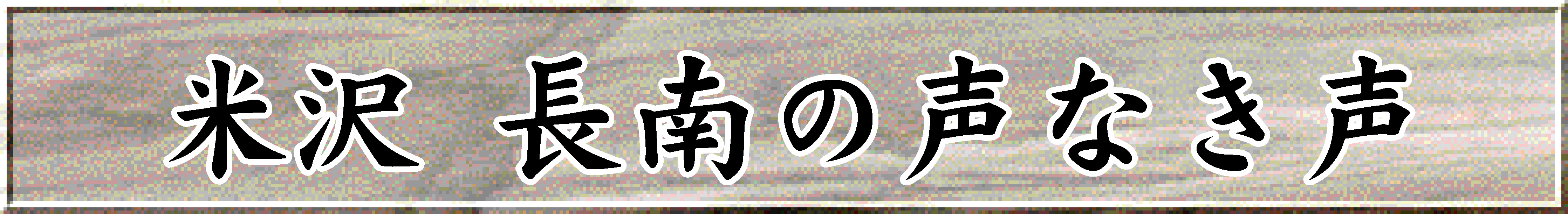
喫緊の課題―ウクライナ、中東、その他でも紛争・交戦、国連の機能不全、戦争の機運がアジア太平洋にも及んで軍事主義(軍事的抑止力・自衛の戦争政策、自衛隊と日米同盟による軍事依存)―防衛費(軍事費)に予算が割かれ、トランプ政権から日本もNATO並みにGDP比5%に増やせと。被団協がノーベル賞受賞にも拘わらず政府は核兵器禁止条約に不参加。学術会議解体法―科学技術の軍事利用へ。エネルギー政策―原発の最大限活用、化石燃料にも依存継続―気候危機。資本主義営利企業・財界本位の経済・財政政策―金権腐敗政治(「政治とカネ問題)、競争格差社会、労働者の低賃金・長時間労働、非正規雇用問題、税制―消費税(庶民負担)重く、法人税・所得税など大企業・高額所得者優遇。年金・医療・介護など社会保障費、教育・福祉予算低減。少子化→人口急減(社会の担い手が縮小)、ジェンダー問題(選択的夫婦別姓の是非)、物価高騰・米問題etc。
今度の参院選で有権者はいったい何を託して投票するのか、主権者としての自覚は?
選挙結果(与野党議席数)はどうなるのか。自公は過半数を割ったとしても、その分野党は国民民主党や維新或いは参政党・保守党など改憲派の方が増えて、改憲派優勢(3分の2以上)には変わらないのか。それでも衆院の方は3分の2を割っており「両院とも」でない限り改憲発議成立はないが、自民党中心の改憲派連立政権であることには変わりあるまい。
これら選挙の結果は国民・有権者の投票の結果によるものだが、それが今の国民の意識なのだということ。それはマスコミやSNSなどのメディア情報の影響によるところも大きいが、これまでの学校教育における政治教育・憲法教育・現代史教育・倫理(人の生き方)など教育のあり方(就職・進学などの受験知識や実利偏重の文教政策でこれらが不徹底)に問題があって、有権者は政治に関する知識・情報リテラシーを充分身に着けてはいないのではなかろうか(戦後憲法制定当初は中学校1年生用社会科教科書として文部省が『あたらしい憲法のはなし』を発行して憲法教育が行われたものの3年間で取りやめ。そこには大戦直後日本を占領したアメリカ軍が日本の民主化・非軍事化を目指し、旧指導層の公職追放を行ったが、対ソ冷戦から朝鮮戦争に至る間に日本を「反共の砦」にしたい思惑から共産党系民主派を公職から追放―所謂「レッドパージ」、反共・再軍備政策に転じた―所謂「逆コース」で平和・民主教育が後退、以来その一途を辿って現在に至っている、という経緯がある)。それがこのまま続く限り、いつまで経っても民主教育・主権者教育は不徹底なものとならざるを得ず、民主主義は形骸化してしまい、ポピュリズムや衆愚政治的な様相が付きまとうことになる。(主権者として自覚と判断に必要な知識の習熟と情報リテラシーが必要なのだ。)
今はコスタリカなど以外には世界のどの国もまともな民主主義国・平和国家はなく、国連の常任理事5大国を始めとして、G7にしてもどれもこれもまともとはいえない。日本は、憲法自体はどの国にもまして民主・平和憲法としてまともなはずなのに、形骸化してしまっており、それとても明文改憲されてしまいつつあり、そうなってはお終いだ。解釈改憲(実質改憲)されてきた憲法は現実に合わせて改憲するのではなく再生・実現を目指さねば。
ホームへ戻る