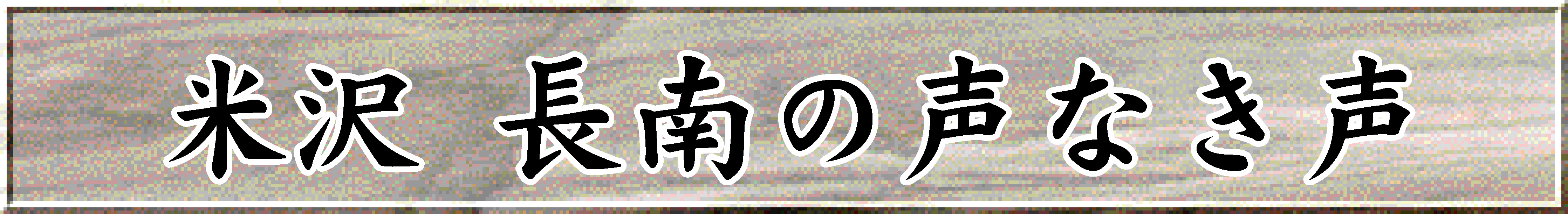
(1)リベラリズムと自由主義
「自由」は英語ではfreedom(「持って生まれた自由」「「先天的・受動的な自由」」)とliberty(勝ち取った自由)「後天的・能動的な自由」)の二通りの自由がある。
リベラリズム(liberalism)の訳語は「自由主義」で、元々は同義語で個人の自由な活動を重んじる思想。
近代(18世紀)欧米で絶対君主や貴族(封建領主)に対して市民が革命で主権(参政権)とともに勝ち取った財産所有権など経済・社会活動の自由権を人権として尊重する考え方なのだが、産業革命後、資本主義経済の発展につれて19世紀後半~20世紀にかけ有産市民(資本家)と無産市民(労働者)との間の貧富格差、労働問題・経済恐慌・失業問題その他社会問題が深刻化し、労働者の権利向上運動や社会主義思想が広まり、第1次世界大戦中ロシア革命などが起こって、その後1919年ドイツで帝国が廃されて新たな共和国憲法が制定され、それに自由権だけでなく生存権など社会権が初めて規定(所謂ワイマール憲法、1933年ヒトラーによって葬り去られてしまったが)。1930年代、世界恐慌に直面したアメリカのルーズベルト大統領(民主党)が打ち出したニューディール政策では失業対策に大規模公共事業などとともに雇用・労働関係法や社会保障法など福祉国家的政策が採られた。それは伝統的な自由主義を修正して政府が積極的に経済に介入する(「社会自由主義」的)路線への転換であった。(アメリカでは同じLiberalismでも、共和党は保守派、民主党はリベラル派と見なされているが、いずれにしろ合衆国憲法には社会権条項はなく、生存権の保障は社会福祉立法によって行われているとのこと。)
第2次大戦でこのアメリカに敗れて占領下に(1946年)制定された日本国憲法には平和的生存権とともに基本的人権として自由権・平等権それに生存権などの社会権が定められた(占領軍総司令官マッカーサーの下で日本の新憲法草案作成に携わった彼の部下たちGHQ民政局スタッフはニューディラーと呼ばれた民主党リベラル派のメンバーだったが、その際かれらが最も注目して参考にしたのがマルクス主義憲法学者・鈴木安蔵を含む日本人有識者たちの憲法研究会が作成した「憲法草案要綱」であり、同研究会が参考にしたのがワイマール憲法であった)。
国連では1948年「世界人権宣言」が制定され、そこには自由権と社会権がともに謳われており、1966年に制定された「国際人権規約」にはA規約として社会権規約、B規約として自由権規約が定められた。
日本では(1955年以来の自民党対社会党・共産党の「保守・革新の対立」という云い方だったのから)1990年代(細川・非自民連立政権~民主党政権の間)「保守対リベラル」という云い方が多用されるようになり、自民党の保守的な自由主義とは違って(社会権を伴う)自由を強調するこの(リベラルという)云い方がなされるようになったと思われる。
(2)そこで
①自由権とは 「どの人も自分の思い通りにすることができるということ」
自分の所有物(身体・頭脳・財産)を何にどう使おうが自由であり、自由に物事を考え、発言し、行動できる権利(思想・信条・言論・表現の自由、経済活動の自由、身体の自由)―自分本位の個人主義―自分のことは自分で決定し、自分に対してだけ責任を負う(自己決定・自己責任)というもので、他人から、或いは国家といえども他から強制も侵害・制約もされず、公権力から干渉や支配を受けず、助けも受けない「権力からの自由」(消極的自由)。
公的領域に対する個人の私的領域の拡大をめざし、国家(権力)から(侵されない)自由(思い通りにできる領域の確保)…生まれ(家柄)や財産による特権・既得権の確保でもある。
国家は個人の活動に干渉・介入は控え、国家の役割は国防と治安の維持など必要最低限の公共事業のみ(「夜警国家」「消極国家」「小さな政府」)。
資本家(企業のオーナー・株主)なら労働者を自分の意のままに扱い(リストラしたり)搾取できる自由でもある。
市場では各個とも自発的に売買・取引できる対等な互酬的関係にあるが、競争(弱肉強食)→勝ち組と負け組に分かれる
大資本と零細業者・労働者など立場によって異なる自由―大資本の自由は弱肉強食の競争や労働者をリストラしたり搾取できる自由。それに対して零細業者・労働者の自由は弱肉強食からの解放、リストラや搾取からの解放などの自由。
②社会権とは 人間らしい文化的な生活を送るために国家に対して一定の公共的配慮(最低限の生活保障)を要求できる権利。
国家(或いは地方公共団体)が積極的に国民の生活に手を差し伸べ、弱者救済や医療・福祉・教育の充実に努める責任を持つ(「積極国家」「福祉国家」「社会国家」「大きな政府」)
国家など公権力から強制・干渉を受けず、助けも受けない「権力からの自由」(消極的自由)に対して「権力への参加(参政権)による(権力による)自由」(即ち民主主義)で積極的自由。
その民主主義の徹底によって労働者・人民が統治への参加権を獲得して権力にありつき、その権力下で(資本主義の矛盾を打開し)経済的隷属から自らを解放し、企業を所有・管理・運営し国民本位に経済を計画的に運用する制度が確立されれば社会主義となる。
そこでは資本家に対して労働者や(大企業に対する)零細業者などの民衆の協同的・集団的連帯性による社会過程への(団結権・団体交渉権・団体行動権などによる)主体的参加が保障される。
権力に対する個々人の自由保障―一つは国家または地方自治体や法人など諸団体の権力(公権力と社会的権力)への主体的参加(「権力への自由」)が保障されることであり、もう一つは政治的圧迫と社会的専制からの自由(「権力からの自由」)が保障されること。個々人にとってはそのどちらかではなく、両方とも必要であり、「権力への自由」のみならず、「権力からの自由」も必要。たとえそれが「自らも参加している民主的権力であっても、本人にとって不本意な、多数者による「圧迫」や「専制」という事態はあり得るし、「圧迫・専制からの自由」というものは、個々人にとって固有な(個人を「自由なる個人」たらしめる前提条件として不可欠な)原則なのだから。
①②とも基本的人権なのであるが、自由主義とリベラルとの違いは、要するに、前者が、市民の自由権でも有産市民(資本家)が企業活動・市場競争の自由などにこだわるのに対して、後者は全ての国民に等しく(自由権だけでなく)平和的生存権とともに人間らしい健康で文化的な生活を営む権利の保障を求める社会権の方にこだわる、その違いなのではと思われる。
(3)つまり自由主義とリベラルの違うところは
①自由主義―自由権の方を重視―個人の利己的権利(財産所有権・営業権)(欲望追求権)
―他人を直接侵害しない限りいかなることも為し得る―有産市民の企業活動・市場競争の自由 (政府の介入排除)を重視-資本主義を擁護・保守
「弱肉強食の生存競争」―弱者に対して「強者の自由」・・・・競争・格差社会
国際関係―国家間の力関係―国家生存・国益追求の国際権力闘争→戦争
現実主義―実利主義(現実に合わせて実利を追求)―「今だけ、カネだけ、自分だけ」(将来世代・諸国民の安心・安全を差し置いて軍備・原発に依存)
新自由主義は18世紀後半のアダム・スミスら古典経済学の現代版「自由放任主義」
で「小さな政府」(民営化・規制緩和、公共事業や公共サービスの削減、弱者保
護のカットなど)を主張
②リベラル―自由権(思想・信条・言論・表現・集会・結社の自由)だけでなく社会権(無産市民・労働者の生活権など)も重視―社会的公正と平等を重視して不平等を是正しようとする。全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れる平和的生存権とともに人間らしい健康で文化的な生活を営む権利の保障を求める社会権の方にこだわる
現実主義でも合理性に基づいて理想追求
国際協調主義―国際協力・国際秩序の構築・国際機関の役割を重視
修正資本主義(近代経済学派のケインズが提唱、資本主義的市場経済に社会主義的計画経済の要素を加えた混合経済)、或いは社会民主主義的「福祉国家」
(福祉サービスを国家が市場や家族を介さずに直接その対象者に提供)―「大きな政府」
・・・・・・ワイマール憲法は言わば「リベラル憲法」
日本国憲法には基本的人権として自由権とともに社会権が規定されており、そのうえ平和主義も規定されていてそれが付け加わって、言わば「リベラル平和憲法」ともいうべきもの。
日本国憲法には「主権在民」と国民の参政権が定められ、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすること」、「全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和の裡に生存する権利を有する」として平和主義が定められ、国は国民の平和的生存権と安全を保障しなければならず、それをどうやって保障するか、然るべき平和・安全保障政策が求められる。基本的人権としては個々人の私有財産権と営業(企業経営・市場取引)の自由、職業選択の自由、居住移転の自由に思想・信教の自由、集会・結社・言論・表現の自由など公権力の介入や他者からの侵害を排除する自由権が定められている。それに加えて平等権と社会権も定められ、全ての国民が等しく人間らしい生活を送れるように国や自治体から保護・支援を得ることのできる「社会権」として「教育を受ける権利」「勤労の権利」「労働基本権」「健康で文化的な生活を営む権利」(社会保障)等も定められている。
(4)そこで、日本の各政党だが、それぞれ立党の目的・政治理念・ビジョンをもち、政策を立てているが、選挙などでは有権者は各政党・候補者を、「はて?どの政党・候補者に投票したらいいものか」と「品定め」する、その際、新聞・テレビ・ネットのSNSや動画、選挙公報、スピーカーから聴こえ見かける姿と声などで「ほ~、いいこと言ってるな」とか「見た目はよさそう、でもな・・・・」とか、色々見立てるものだが、その場合どこに焦点をあてるか、一番大事なところはといえば、その政党・候補者の基本的な考え方(基本理念)はどうなのか、憲法の理念と合わせて見定めること、それにその党・候補者はいったいどういう境遇や立場の人たちの身になって考え話しているのか、その心根を見極めることなのではあるまいか。
各党は、それぞれどんな政治理念を持っているのか、憲法の理念と合わせてそこのところはどうなのか。幾つもある政党だが現行憲法(リベラル平和憲法)に照らせば、そのリベラルと平和主義の観点から各党は二派に分けられるのでは。つまり「ざっくり言えば」現行のリベラル平和憲法に①「違和感を持たず、なじんでいる」派(わざわざ変えなくてもいいという護憲派)か、②「違和感を持つ」派(変えた方がいいという改憲派)かだ。それぞれ温度差はあるが、大まかに次のように分けられるのでは。
①の方には立憲民主・共産・社民・れいわ・新社会党など。
②の方には自民党・維新・参政・保守・国民民主など。
(5)先の衆院選の結果、これまでの自民党「1強」から自民・立憲「2強」になって、自民党Vs立憲民主党が対立軸となってその他の中小の政党はそのどっち側かに分かれて2大陣営が形成され政権交代ができる形にはなってきた。自民党側と立憲民主党側の両陣営の勢力が拮抗していれば、第三党・中間派か少数政党でもキャスティングボード(決定権)を握れることにもなり、それがどっちに付くかで、立憲民主党の側に付けば政権交代もあり得、さもなければ自民党側の政権が延命する結果となる。
首相指名選挙の決選投票では自民党首の石破氏が221票、立憲民主党首の野田氏が160票、無効票が84票で石破氏が首相に再選された。その無効票は、共産・社民以外の野党(維新・国民民主・れいわ・参政党・日本保守党など)でこれらの野党議員が「野田」と明記して有効票を投じていれば、合計で石破票を上回って野田氏が首相となって立憲民主党の方に政権交代もあり得たはずが、そうはならず、自民党の石破政権が延命する結果となった。(それを決定づけたのは維新・国民民主党など共産・社民以外の野党の投じた無効票・・・・そんな結果をもたらす「キャスティングボード」の役割もあるわけである。)
(6)各党とも、それぞれ独自性をもち、「一人我が道を行く」といった向きもあるのだろうが、政権交代を念頭に、自民・立憲「2強」が対立軸になって2大陣営対決の構図を描いて、その両陣営の対立する政治理念・基本政策等を対称表に列記すると次のようになる。
自民党陣営 ←―――――――|―――――→ 立憲民主党陣営
政治理念 自由主義 ←―――――――|――――――→ リベラリズム
自由権(個人の自由・ 自由権(思想・信条・言論・表現
諸権利―財産私有権 集会・結社の自由)
起業・営業・取引 社会権(社会的公正・平等
の自由など)を重視 社会保障・勤労権・労働三権・
企業の政治活動(政治献金も)自由 教育を受ける権利など)を重視
新自由主義―市場原理主義(自由競争主義) 共生社会 共助・公助(福祉)を重視
政府による市場への介入を排した「小さな政府」 格差是正、これらに対する政府
―規制緩和・民営化 の積極的役割を重視―「大き
競争・格差社会 自助・自己責任を重視 な政府」
現実主義―実利主義 現実主義でも合理性重視し理想追求
保守主義―伝統的価値観に囚われ現状維持←――|――→ジェンダー平等・選択的夫婦別姓
(天皇制・靖国参拝・家族主義 重視) が望ましい、多様性 重視
安全保障―軍事 重視(「タカ派」)←―――――|――――→平和外交の重視(「ハト派」)
日米同盟を基軸―――――――――――――――→継続
安保法制(集団的自衛権行使の限定的容認)――→違憲部分は廃止?
アメリカの「核の傘」に依存
核兵器禁止条約には不参加―――――|―――→参加望む
現行憲法(リベラル平和憲法)の「改正」に積極的←―|―→消極的か護憲
(前向き) 現行憲法尊重(立憲主義)
原発 推進派←――――――――――――――|-――→脱原発派
企業献金に依存←―――――――|―――――――――→禁止
自民党陣営(改憲派陣営) ←―――|――→立憲民主陣営(リベラル護憲派陣営)
維新・参政・保守党 共産・社民・れいわ・新社会
公明・国民民主党
(ここで「立憲民主陣営」といっても、立憲民主党がリベラルの「旗頭」というわけではなく、この陣営内では議席数で最大多数勢力だからにほかならない―立憲民主党と陣営内の各党とは対等関係。)この対立する2大陣営を峻別する基準は現行憲法(リベラル平和憲法)に対して改憲に前向きな改憲派か、単なる自由主義・形式的民主主義ではなく平和的生存権・社会権・平等権を定める憲法を大事にして名実ともにその理念・条項を守り生かし切る護憲派(或いは改憲には後ろ向きで消極的な立場)かということで、改憲派Vs護憲派の対決となるのかどうかだ。しかし肝心の立憲民主党に自民党・改憲派に対決すべく護憲派の側に立って共闘体制を組もうとする自覚(自分たちは共にリベラル派で平和憲法護憲派だという自覚)があるのかといえば、「?」だ。
先の衆院選の直前、(「朝日・東大共同調査」で各党候補者に選挙後の連立政権の相手について考えを質問)立憲の候補は、国民民主と「組むべきだ」・「あり得る」合わせて95%、維新とも「あり得る」(60%)が「あり得ない」(40%)を上回り、共産党とは「あり得ない」が72%に上った。また野田代表は維新・国民民主党とは「あり得る」が共産党とは「あり得ない」と。(共産党の候補は「あり得る」が72%だったが、田村委員長は、自民・公明・維新・国民民主とは「あり得ない」で、立憲については無回答だったという。)立憲民主党は先の衆院選では山形県2区では国民民主党候補を推して、来夏の参院選では立憲民主党は山形県選挙区では連合系労組とともに国民民主党会派の候補を推すようだが、全国的には国民民主党と護憲派(共産・社民・れいわ)のどっちと共闘を組むのかだ。護憲派と組んでその候補者が多く当選すれば、今回の衆院選と同様に、参院でも改憲発議阻止に必要な3分の1以上の議席が確保できることにはなるのだが。いずれも立憲民主党次第ということになるが、市民連合や9条の会など護憲派市民団体の「後押し」「盛り上がり」次第でもあるだろう。
(このような、憲法が「どうのこうの」、リベラルが「どうのこうの」と云って、「二大陣営の対立構図」など考えたりしているのは「自分で勝手に思っている」一人合点で、オールドメディア(マスコミ)でもニューメディア(SNSやユーチューブ)でも問題にされない絵空事に過ぎないのかも。)
(7)企業・団体献金について
2月の国会(衆参両院の本会議)で共産党(企業・団体献金全面禁止法案を提出している)の代表質問―「企業が献金によって行う政治活動とはカネの力で政治を動かそうという利権政治そのもの。」「投票権を持たない企業の政治献金は国民の参政権を侵害するものではないか」と。
ところが、それに対して岸田首相の答弁―「企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄付の自由を有するとの最高裁判決があるにもかかわらず、企業・団体献金がカネの力で政治を歪め、国民の参政権を侵害するというのは論理の飛躍があると考える」と。ここで首相の言う「最高裁判決」とは上記の1970年の八幡製鉄政治献金事件裁判を指すものと思われるが、そんな半世紀も前の判例を持ち出しての答弁。(「論理の飛躍がある」のは首相の方では?)
この最高裁判決後、ロッキード事件(1976年)・リクルート事件(88~89年)・佐川急便事件(92年)などを受けて1994年の非自民連立政権の細川首相と自民党の河野洋平総裁との党首会談で、企業・団体献金を(企業との癒着防止ため)禁止(その代わり政党助成金制度を創設)することに合意。ところが1999年政治資金規正法改定で、それが政治家個人に対する献金禁止だけにとどまり、政党本部及び支部に対する献金とパーティー券購入の形でならOK(合法)というふうに「抜け穴が」残された。それを共産党は「約束の反故」だとしており、河野・当時自民党総裁は「公費による政党助成が実現したら企業献金は本当に廃止しなきゃ絶対おかしい」と証言している。
経団連(十倉会長は住友化学の代表取締役会長)は(2004年から企業献金の斡旋を再開)今に至るまで、主要政党の「政策評価」(毎年発表し、経団連の求める政策の推進・「実績」を評価し「課題」を提言)を基に献金を「社会貢献」と称して会員企業に呼び掛けている。
(経団連が求めてきた政策―消費税増税と法人税減税、社会保障削減策、労働法制規制緩和、原発再稼働の推進)(会員企業のうち電力会社など原発利益共同体企業から自民党への献金は2023年6億円超)
その結果、噴出したのが近年の政治資金パーティーをめぐる巨額の裏金問題なわけである。
企業・団体献金が自民党に対して行われ、それが政党から派閥幹部、そして所属議員に「政策活動費」などの名目で配られた場合、配られた議員はその使途を収支報告書に記載して公開できるようにしなければならないはずが、その記載がなく使途不明で何に使われたか分からない「裏金」―「不正行為の温床」になっているということで、「裏金事件」として持ち上がったのが、この問題なのである。
一橋大憲法学の江藤祥平教授の見解(2月8日付朝日)
①「政治活動の自由」は憲法21条にある「表現の自由」が根拠だが、歴史的には権力を監視する「出版の自由」がルーツなのであって、政治家にとっての「自由」として発展したものではない(政治家の側が、これを盾として民主主義の健全性を歪めてもいいと思っているなら滑稽というほかない)と。
②八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決では(「公共の福祉に反しない限り、会社と云えども政治資金の寄付の自由を有すると云わざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するとなす論旨は採用のかぎりでない」とのことだが、そうした政治資金寄付などの自由が金権政治や政治腐敗など弊害を生むことも指摘)「弊害に対する方途は立法政策を待つ」としており、実際に弊害が生まれているならば、立法府は公共の福祉を根拠に制限をかけて然るべきで、制限したとしても「政治活動の自由」に反するわけではない。そのために企業・団体献金の質的・量的な制限は当然認められ、「政治とカネ」の問題が深刻化している現状では「原則禁止」とすることも憲法上許容されるだろう、と。
③「国民の知る権利」のためだからといって「使途記載」が義務付けられて公開され、企業・団体の営業秘密が侵害され、党の戦略的な運営方針が他の政治勢力や諸外国に対して秘匿できなくなっては困る、という言い分については、それは外交機密など高度な政治性を帯びている場合に限られ、それ以外には政策活動費など使い道は公開されて然るべき。政党が用いる資金は公の性格を有し、汚職や賄賂など公的な問題が生じうる限り、当然に「知る権利」が優越。むしろ、政党に渡されたカネがどのように個人や企業に流れているのかは、国民が知っていた方が投票の際の判断材料にもなるのだ、と。
そもそも憲法21条(集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由)に基づく「政治活動の自由」とは国民(自然人たる個人)に対して保障することを定めたものであって、国民の「知る権利」(情報を国など権力に妨げられることなく収集し公開を求めることができる権利)とともに主権者たる国民の選挙権・参政権に必要不可欠もの。(企業・団体ではなく個人としてなら、応援したい政党や政治家個人にも、それらが指定する資金管理団体や後援会には限度内でカンパ・献金もできる。)
それに対して政治資金規正法(1948年制定後、75年・92年・94年など幾度か改正)は政党その他の政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が、国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためのもの(同法第1条)で、企業(法人)なども共にその規正の対象なのであって、政党・政治団体の「政治活動の自由」や企業・団体の献金・寄付の自由を保障するためのものではないのだ、ということだろう。
それにつけても自民党の巨額裏金問題―自民党派閥に業・財界からパーティー券代として寄付・献金された大ガネが政治資金収支報告書に不記載・使途不明―自民党内でシステム化していた組織的「裏金づくり」―政治資金規正法違反の組織的犯罪―自民党内で多くの所属議員(自民党の身内の調査で党内派閥、安倍派・二階派など所属議員91名)が20年とか何年にも渡って行われていた―そのような政党が最大多数党となって長期にわたって君臨してきた政権は今こそ非自民党政権に交代させなければならない―憲法による国民の主権・政治活動の自由を「カネと力ある者」の自由と履き違えている憲法歪曲(ブルジョア的憲法解釈)・改憲政党で財界親和政党を、庶民の立場に立って憲法を正しく守る護憲派の連合政権に交代へ。
自民党は企業・団体からの政治献金を他党(2023年、各党支部への分を除き本部への分だけで立憲民主党76万円、れいわ69万円、維新35万円、国民民主党30万円その他はゼロ)に比して圧倒的に多額の献金(23億円)を受けているが、岸田政権が裏金問題で退陣して代わった石破政権が解散・総選挙に打って出たものの議席を大幅に減らして辛うじて政権を維持し少数与党となった今もなお「法人」企業・業界団体には経済活動とともに政治活動の自由の一環として政治献金も憲法上認められているはずだとして正当化している(「個人献金は善で企業・団体献金は悪だとは思はない」「浄財」だと)。
憲法では21条に集会・結社(政党・政治団体などの結成・入党・入会して活動)・言論・出版その他一切の表現の自由は認めている。
一方、12条には「この憲法が国民に保障する自由および権利については、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のために利用する責任を負う」、13条には「全ての国民は個人として尊重される。生命・自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共に福祉に反しない限り立法その他国政の上で最大の尊重を必要とする」、15条(国民の参政権について)「公務員を選定し、及びこれを罷免することは国民固有の権利である」、44条(選挙権・被選挙権について)「選挙人の資格は法律でこれを定める。但し人種・信条・社会的身分・・・・財産又は収入によって差別してはならない」などと定められている。
いずれも国民一人ひとりの権利(一人一票の平等選挙など、個人として為し得る権利)を定めたものであって法人組織(企業・団体)の権利を定めたものではない。
企業(会社)にしても業界団体にしても労組・宗教団体などにしても、それぞれ組織の構成員(株主・経営・管理層・従業員労働者・正規・非正規・労組役員・一般組合員・幹部信者・一般信者など)の共通利益の確保・組織内外との利害調整・団体交渉・対外的アピール・圧力団体機能などの役割(効用)があるわけであり、その組織としての活動の自由・権利は認められ、企業なら営業・経済活動の自由があり、その一環として(営業・経済活動に関連する)政策提言など、政治活動の自由もそこまでは容認。しかし企業・団体として政党への政治献金となると、それは自由権の濫用となる。何故なら、その企業・団体の組織が(政党の党員のように)初めから構成員全員が思想・信条を共にするシンパ(同調者)から成る特定政党の支持団体(後援会などの政治団体)で、会員が全員合意の下に出し合った会費から献金する、という場合(即ち同じ思想・信条を持ち同じ政党支持の意思を持つ者同士という個人の集合体)ならいざ知らず、そのような政治団体でもない営利目的の企業や業界団体、労働者としての権利確保を目的とする労組、同じ教義を信じ布教・礼拝儀式行事を行い信者の強化・育成を目的とする宗教団体などの場合は構成員各人が政治に対する思想・信条もみんな同じで支持政党も同じだとは限らず、国政選挙などではどの政党・候補者に投票しようと自由(自分の勝手)である以上、応援活動とともに資金カンパ(個人献金)も自由意志で行うもの。それを自分が所属するその会社や業界・労組・教団が(組織の上部・代表役員の権限で、或いは社員・組合員・信者など多数決で決めたとしても)自分の意に反した政党支持を強いてはならないのと同様に、自分の意に反した献金も(その金額には、いささかなりとも自分が稼ぎ出したか、納めた分が含まれており、それが自分の意に反した政党への献金に使われてしまうというようなことは)やってもらっては困るわけである。(その意味では政党交付金も同じことで、全ての納税者・国民が自分の納めた税金から―たとえ「コーヒー一杯分」とは云え―支持政党でもないのに議席に応じて各党に配られる―自民党には156.5億円、立憲民主党には70.5億円、維新には33.6億円、公明党には28.6億円、国民民主党には12.6億円、れいわ6.7億円、社民2.8億円、参政党2.4億円、保守党0.2億円。そんな不合理なことってないわけである。)
会社、或いは労組・教団など「ぐるみ」でその予算・経費から割いて特定の政党への政治献金に支出をするというのは不当であり、企業・団体献金はそれこそ憲法に抵触する違法なものであり、禁止されて当然。
現行憲法は(ブリタニカ百科事典などで分類している)「ブルジョア憲法」なんかではなくリベラル憲法の立場で、リベラル野党の主張はそのリベラル憲法に則っている。その憲法をねじ曲げて企業・団体献金を正当化し、禁止を拒んでいる自民党の考えはリベラルではない自由主義的なブルジョア的(企業資本家本位の)「自由」の立場で、党の財政の大部分を企業・団体献金に依存(大企業・財界は云わば「金づる」)。そしてその政策は、(経済・産業・金融・税制・安全保障政策にしても)財界の意向に沿いその要望に応じた政策を優先しており、自民党は「国民政党」と云いながら、ブルジョア政党で、財界の「利益代表」的政党ともいうべき性格が表れている。
憲法をブルジョア改憲派によってブルジョア憲法にされてしまうことのないように、リベラル派野党はこのリベラル平和憲法を護る護憲共闘に自覚的に結集し取り組まなければなるまい。(リベラル派って?それは要するに、資本家など有産階級ブルジョア派に対して中産・無産階級「庶民派」ということなのでは。)
ホームへ戻る